
くら寿司が中国全店撤退と報道されたのが7月頭。店舗は撤退すれど法人は残るとのことなので、今後の展開を見据えた動きに入っているのだと思いますが、今後に期待したいところです。
日系の回転ずしとしてはま寿司とスシローも参入してきており、くら寿司の撤退報道の頃にこの2社とどう違ったのかという記事は多くみられました。ここではそれを話題にせず、違うテーマで書いてみたいと思います。
KURA寿司公式wechatサイトより参照
くら寿司中国撤退の背景と特許無効問題

個人的に気になったのはくら寿司が中国で申請していた特許が当初は認められたにもかかわらず、後から無効宣告されたことです。対象となった特許は以下の3つです。
賞品生成装置
くら寿司が中国で取得した特許「奖品生成装置(ZL202220253509.7)」は、同社の人気サービス「ビッくらポン!」に関連する景品提供システムに関する技術です。これは、回転寿司を楽しみながら、一定数の皿を取るとガチャガチャのように景品が出てくる仕組みを支える装置で、エンタメ性と顧客満足度を高めるものです。
食器回収システム
くら寿司が中国で取得した実用新型特許「餐具回收系统(ZL202220377814.7)」は、使用済みの寿司皿などの食器を自動で回収するシステムに関する技術です。これは、くら寿司の店舗でおなじみの「皿投入口」に関連する装置で、顧客が食べ終えた皿を投入口に入れると、自動的に回収・集積される仕組みを支えるものです。
報酬システム及び報酬方法
くら寿司が中国で取得した発明特許「报偿系统及报偿方法(ZL202080035352.4)」は、同社の人気サービス「ビッくらポン!」をさらに高度化した報酬(景品)提供システムとその方法に関する技術です。これは、単なる装置ではなく、注文情報・座席情報・皿回収状況などを統合的に判断して景品を提供する情報処理システムに関する発明です。
これらの特許申請はいずれも認められていたのですが、無効宣告請求がどこかから出され、その無効宣告請求が認められたことによりこれら特許は無効となったようです。いずれも「創造性がない」という理由で無効宣告されています。「この発明は、すでにある技術を少し組み合わせただけで、新しい工夫とは言えない」と判断された、ということです。もう少し細かく説明すると、「蔵寿司のこの特許の核心的な考え方は、食事体験と抽選ゲームを結合して、寿司皿の回収数で売り上げを確定し、抽選メカニズムをトリガーすることにすぎない」と判断されたということです。個人的にはどれもこれも素晴らしいと思うのですが、残念な結果になっています。
中国におけるビジネスモデル特許の難しさ

KURA寿司公式wechatサイトより参照
私の中ではこれはビジネスモデル特許のイメージでした。ビジネスモデル特許とは、「商品やサービスの提供方法、収益構造、顧客体験の設計など、ビジネスの仕組みを技術的手段で実現する発明に対して認められる特許。」のことをいいます。特許として認められる条件として日中で共通しているのが、
- 技術的課題を解決していること
- 技術的手段で実現されていること
- 単なる商業アイデアではないこと
くら寿司のこれはは該当すると思いますし、調べたところAmazonのワンクリック購入もこれに該当するとのことです。
3件の特許(装置・システム・方法)が同時期に無効宣告されたことから、戦略的にまとめて請求された可能性が高いように思われます。同じようなサービスを導入しているところとして一社思い浮かぶところがありますが、果たしてそこが無効宣告申請を提出したのか。中国の特許無効審判では、請求人の氏名や企業名が審決文に記載されない限り非公開なため、確証はないのですが気になるところです。
無効宣告が企業戦略に与える影響とは
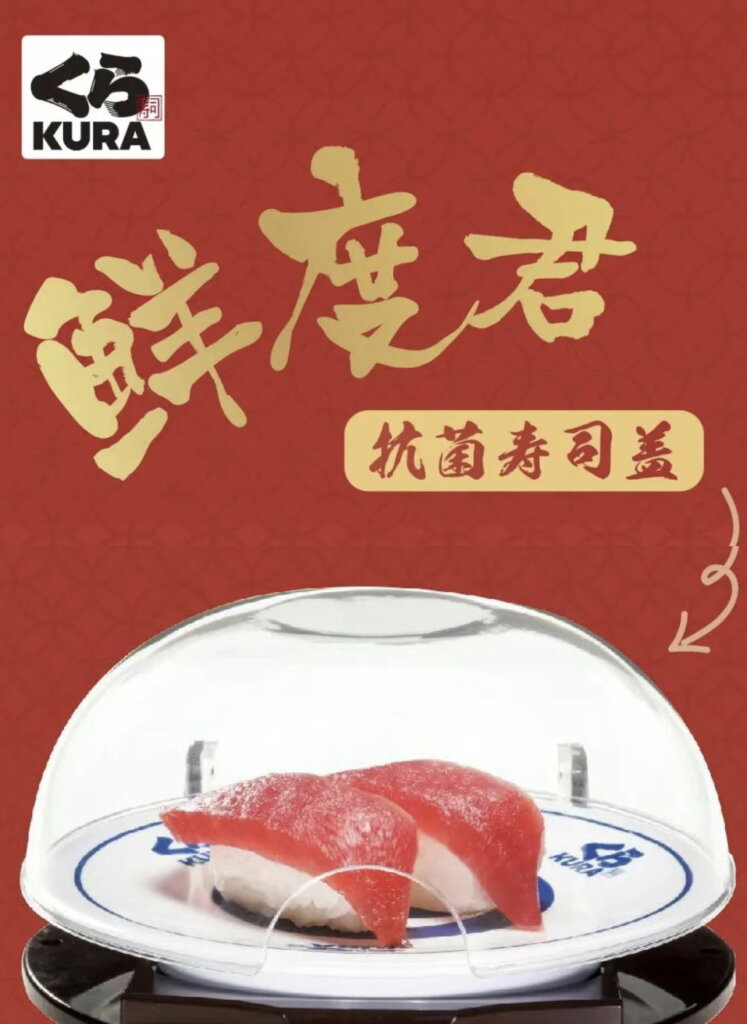
特許の無効宣告請求されたのが2025年3月28日、無効宣告決定日が2025年8月2日、そしてくら寿司全店撤退報道が出たのが2025年7月2日。そのため、無効宣告が直接的にくら寿司撤退の原因となったとは言えないと思うのですが、無効宣告請求された時点でストレスは感じていたのではないかと思います。
しかし、いったん認められた特許が後から無効宣告されるとは思いもしなかったのではないでしょうか。日本でも特許の無効宣告は制度としてあり事例としてもあるので、中国で同じことがあっても不思議ではないのですが、当事者としては何とも合点がいかない感じを持たれたのではないでしょうか。また、中国で特許を持つ企業にとって、この無効宣告リスクというのも今後は考えていく必要もありそうですね。
KURA寿司公式wechatサイトより参照








